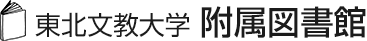紀要第1集(1967)
| 芭蕉作不審句二三について | 小林 正治 |
| “文獻”考 | 平沢 東貫 |
| 兼好の兄兼雄と明忍 | 林 瑞栄 |
| 今昔物語集巻十六の文章 | 佐藤 武義 |
| 漱石の女性像 -「草枕」「虞美人草」「三四郎」をめぐって- | 高橋 美智子 |
| 仏身思想の源流について | 石川 海浄 |
| 寒河江市平塩の熊野神社 | 月光 善弘 |
| ろう難聴児の発話学習についての一考察 | 新谷 守 |
| 国民学校初等科教科書内容分類(修身・国語) | 八本木 浄 |
紀要第2集(1968)
| 横川と兼好-兼好と出家に関する一考察- | 林 瑞栄 |
| 今昔物語集巻19の文章 | 佐藤 武義 |
| 「行人」の一郎と二郎 | 高橋 美智子 |
| 瑞宝山慈恩寺の組織について | 月光 善弘 |
| 教育審議会に於ける国民学校教科課程案の成立 | 八本木 浄 |
| 国際教育学序説(その3) -民族文化形成と他民族文化との交流- | 小林 一男 |
| ペスタロッチーに於ける直観思想の萌芽とその展開過程について | 細井 房明 |
| 盲ろう者におけるCommunication と Rehabilitation についての実験的研究 -文献研究と調査- | 新谷 守 |
| 一場の等角写像夢 | 黒田稲夫 |
紀要第3集(1969)
| 続・横川と兼好-その信仰生活と現実- | 林 瑞栄 |
| 漱石の自己本位について | 高橋 美智子 |
| 中尊寺一山の組織と変遷 | 月光 善弘 |
| 国際教育学序説(その4)-幕藩経営より国家経営への過程- | 小林 一男 |
| ペスタロッチーの教育思想-直観の機能と術の必要性について- | 細井 房明 |
| 心身障害児の発生予防と福祉 | 新谷 守 |
| 「体育」の立場から美についての一考察 | 庄司 光子 |
| 単位円内正則正規化単葉関数族の一展望Ⅲ | 黒田 稲夫 |
紀要第4集(1970)
| 「兼好家集」の邦良皇太子との連歌の示すもの | 林 瑞栄 |
| 王夫之の思想 ─その基調をめぐる一考察─ | 黒坂 満輝 |
| 「浅茅が宿」試論 ─勝四郎像をめぐって─ | 勝倉 寿一 |
| 毛越寺一山の組織・変遷および平泉地域と修験 -密教-との関係 | 月光 善弘 |
| 生活周期と生活計画(その一)─地域社会における婦人生活を通じて─ | 小林 一男 |
| 死刑についてのペスタロッチーの見解 | 細井 房明 |
| ある似真(共形,等角)写像について | 黒田 稲夫 |